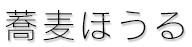
古淡風雅の味
京都ではかつて、菓子屋が蕎麦を打っていた時代があったといわれる。今のように日常的に蕎麦を食べなかった時代、必要なときに、お寺などが菓子屋で蕎麦をあつらえていたのだ。菓子屋には粉を扱う技術と道具が揃っていたからである。
そういう時代の面影を、今に伝えているのが、京都の蕎麦の老舗として名高い河道屋だ。
河道屋は、蕎麦の晦庵河道屋と、菓子の総本家河道屋に分かれている。
創業は元禄時代、初め一つだった店を、14代目が隠居仕事のために建てた晦庵を蕎麦専用に、本店を菓子だけを扱う店としたようだ。総本家河道屋は、以前はいろいろなお菓子を作っていたが、今は、明治初期に12代目植田安兵衛が創案した銘菓「蕎麦ほうる」ただ一品しか製造販売していない。両河道屋の現在の当主は、16代目の植田貢太郎さんである。
「蕎麦ほうる」の「ほうる」は、「ぼうろ」と呼ばれる菓子と同じくポルトガル語からきていて、南蛮菓子の製法を取り入れた、というほどの意味だ。蕎麦粉、小麦粉、砂糖、卵を材料とする焼き菓子で、形もシンプルに梅の花と蕾をかたどった2種類だけ。口に入れると、蕎麦の香りが広がり、さっと口溶けする、いってみれば和風クッキーの傑作である。 缶入りの「蕎麦ほうる」を開いてみることにしよう。まず、包装紙が好もしい。型押しのように見える細かいストライプの入ったアイボリー系の地色に、濃い緑色で「蕎麦ほうる」そのものの梅の花と丸い蕾が、不規則に散らしてある。上品で、どこか懐かしさを感じさせるデザインだ。
包装紙をはずすと、全面模様の缶。紫系の色で印刷されているのは、茶室の天井などによく見かける、篠竹を細かく編んだ模様だ。正面に、商品名と店の名を墨書した和紙が貼りつけてある。缶は二次利用しやすいように、蓋に文字を印刷していないとのこと。心配りが缶のたたずまいにも、温かく表れている。 缶を開けると、薄紙を透かして、ほっこりとした色の「蕎麦ほうる」が見えた。すぐに手が出る。京都にこの古淡風雅な味が伝えられていることを思うと、頼もしく、嬉しくなってくる。 堂々たる老舗が、この一品だけを守って悠々と商いを続けていることこそ、まさに風流というべきだろう。
総本家河道屋
京都市中京区姉小路通 御幸町西入ル
TEL 075-221-4907
![]()












