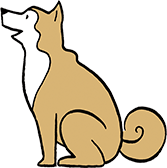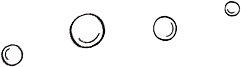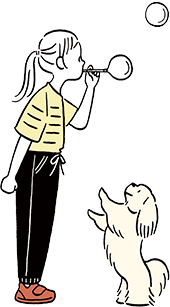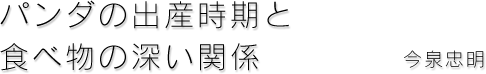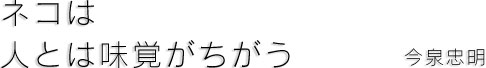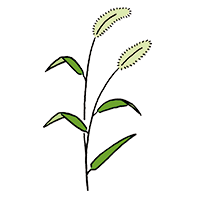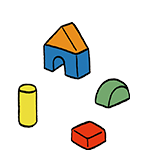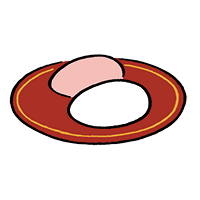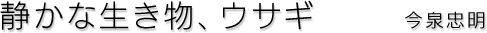

ウサギは静かな生き物である。不満があってもギャーギャー騒がず、楽しいといった顔も見せない。落ち着いた風情がある。だからと言って不満がないわけでも、毎日がつまらないわけでもない。不満があれば大きな後足で地面をバタンバタンと叩くし、楽しければ走ってピョ〜ンと高く跳んで、空中で両方の後足を拍手のようにポンと打つ。
考えてみれば、ウサギは不思議な体つきをしている。見慣れているからか、ウサギの耳が長いことは当たり前に思っているが、ゾウの鼻が長いのと同じくらい奇妙だ。
以前、カリフォルニアの平原でジャックウサギが走っているのを見つけた。これはいい機会だと、二手に分かれて挟み撃ちにして草むらに潜んだところを写真に撮る計画を立てた。膝の高さくらいの草の間をガサゴソとゆっくり進んでいったとき、目の前からいきなりウサギが跳び出した。ピョーンと高く跳び上がったかと思ったら、あっという間に地平線まで続く草原の果てに消えていった。まさに脱兎のごとく、実に速い。声も出さず、音も立てずに、消えていった。
ウサギは静かな生き物なのである。

illustration by 小幡彩貴
|
||||